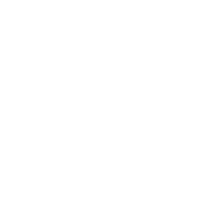
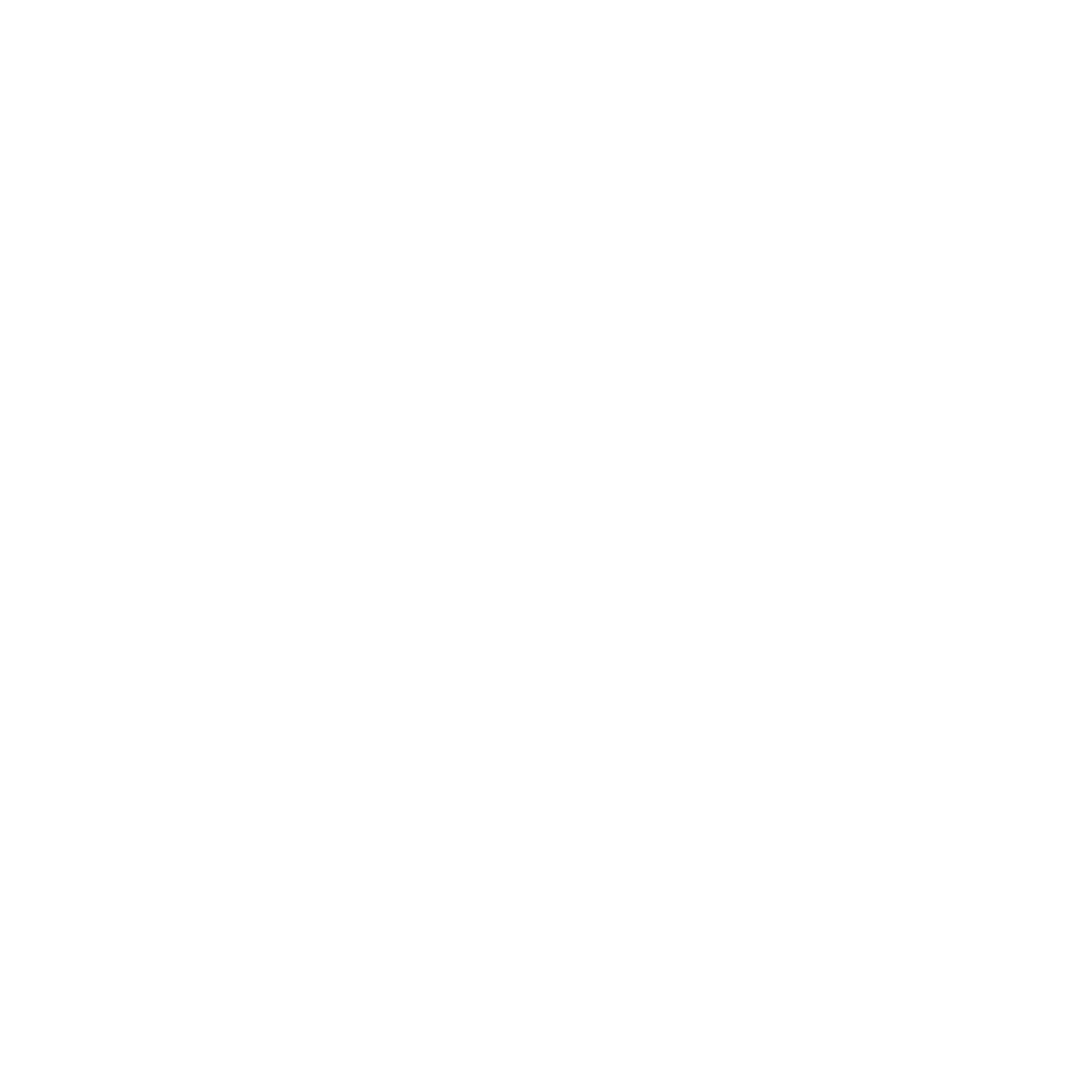
2024年度診療報酬改定に伴い、オンライン資格確認等システムが導入されることを踏まえ、当ステーションでは訪問時等に利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用して訪問看護に関する計画的な管理を行い、質の高い医療の提供を目指しています。
これにより訪問看護DX情報活用加算として定められた額を諸定額に加算します。
令和7年2月1日より算定 訪問看護医療DX情報活用加算 50円
【訪問看護医療 DX 情報活用加算の施設基準】
(1)厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること。
(2)マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えていること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
2025年2月
ハート&ハート訪問看護ステーション
管理者 吉田 博美
2024年度診療報酬改定に伴い、オンライン資格確認等システムが導入されることを踏まえ、当ステーションでは訪問時等に利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用して訪問看護に関する計画的な管理を行い、質の高い医療の提供を目指しています。
これにより訪問看護DX情報活用加算として定められた額を諸定額に加算します。
令和7年2月1日より算定 訪問看護医療DX情報活用加算 50円
【訪問看護医療 DX 情報活用加算の施設基準】
(1)厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること。
(2)マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えていること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
2025年2月
ハート&ハート訪問看護ステーション
管理者 吉田 博美
1 目的
株式会社ハート&ハートが開設する介護保険サービス等事業所(以下「事業所」という。)は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく従業者一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体的拘束をしないケアの実施に努めることにより、利用者へのサービスの向上を図るため本指針を定める。
2 身体的拘束廃止の規定
利用者等本人または他の利用者の生命または身体が危機にさらされる可能性が著しく高いこと。
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3 身体拘束廃止のための基本方針
身体拘束を廃止するための基本方針は、次のとおりとする。
原則として身体的拘束及びその他の行動制限を禁止する。
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、事業所内において十分な検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクの方が高く、切迫性・非代替性・一時性の三要件全てを満たした場合のみ、本人及び家族へ説明し同意を得てから行うものとする。また、身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるかぎり早期に拘束を解除すべく努める。
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
4 身体拘束等適正化に向けた体制等
身体拘束等適正化の継続的な実施に取り組むため、次のような体制を整備し運営するものとする。
各事業所及び施設において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、リスクマネジメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会は、社長・事業部長・管理運営部長・リスクマネジメント委員で構成する。
委員会は、年1回以上開催するものとする。ただし、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合は、身体拘束の実施状況や三要件を具体的に検証するため別に開催するものとする。
5 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
6 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応等
事業所は、本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
緊急やむを得ない状況になった場合、検討委員会を中心に、拘束による利用者の心身の損害や、拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて十分に検討、確認する。
身体拘束の態様および目的、身体拘束を行う時間、時間帯、期間等とともに改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者および家族等に現在行っている拘束等の内容と方向性、利用者の状態などを確認・説明し、同意を得たうえで拘束の延長を実施する。
身体拘束に関する記録は、専用の様式を用いてその様子、心身の状況およびやむを得なかった理由などを記録する。また、身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録は提供サービス完結の日から2年間保存するとともに、行政等による指導監査が行われる際に迅速に提示できるようにする。
上記(3)の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除するとともに契約者および家族に報告する。
7 身体拘束等の適正化のための研修等
事業所は、介護に関わる全ての従業者に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図るため、従業者への教育、研修を定期的かつ計画的に行う。
(1)定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。)
(2)新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
8 利用者に対する本指針の閲覧について
本指針は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。
またホームページ等にも公表し、利用者および家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
1 目的
株式会社ハート&ハートが開設する介護保険サービス等事業所(以下「事業所」という。)は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく従業者一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体的拘束をしないケアの実施に努めることにより、利用者へのサービスの向上を図るため本指針を定める。
2 身体的拘束廃止の規定
利用者等本人または他の利用者の生命または身体が危機にさらされる可能性が著しく高いこと。
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3 身体拘束廃止のための基本方針
身体拘束を廃止するための基本方針は、次のとおりとする。
原則として身体的拘束及びその他の行動制限を禁止する。
本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、事業所内において十分な検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクの方が高く、切迫性・非代替性・一時性の三要件全てを満たした場合のみ、本人及び家族へ説明し同意を得てから行うものとする。また、身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるかぎり早期に拘束を解除すべく努める。
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
4 身体拘束等適正化に向けた体制等
身体拘束等適正化の継続的な実施に取り組むため、次のような体制を整備し運営するものとする。
各事業所及び施設において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、リスクマネジメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会は、社長・事業部長・管理運営部長・リスクマネジメント委員で構成する。
委員会は、年1回以上開催するものとする。ただし、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合は、身体拘束の実施状況や三要件を具体的に検証するため別に開催するものとする。
5 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
6 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応等
事業所は、本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
緊急やむを得ない状況になった場合、検討委員会を中心に、拘束による利用者の心身の損害や、拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて十分に検討、確認する。
身体拘束の態様および目的、身体拘束を行う時間、時間帯、期間等とともに改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者および家族等に現在行っている拘束等の内容と方向性、利用者の状態などを確認・説明し、同意を得たうえで拘束の延長を実施する。
身体拘束に関する記録は、専用の様式を用いてその様子、心身の状況およびやむを得なかった理由などを記録する。また、身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録は提供サービス完結の日から2年間保存するとともに、行政等による指導監査が行われる際に迅速に提示できるようにする。
上記(3)の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除するとともに契約者および家族に報告する。
7 身体拘束等の適正化のための研修等
事業所は、介護に関わる全ての従業者に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図るため、従業者への教育、研修を定期的かつ計画的に行う。
(1)定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。)
(2)新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
8 利用者に対する本指針の閲覧について
本指針は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。
またホームページ等にも公表し、利用者および家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
「御用聞きサービス」→ 「暮らしのお助けサービス」に名称変更
医療・福祉サービスでは手が行き届かない部分まで支援の幅を拡げ、一歩踏み込んだサービスを展開
自宅で生活する上で必要になってくる日常生活関連のお困り事をお助けするサービスです。
草取りや家の大掃除、買い物の代行、庭の手入れ、除雪やタイヤ交換、電球の交換など幅広く対応が可能です。
自宅生活を送る中で、一人ではできない、家族に頼れないといった時には頼って頂きたく思います。
「御用聞きサービス」→ 「暮らしのお助けサービス」に名称変更
医療・福祉サービスでは手が行き届かない部分まで支援の幅を拡げ、一歩踏み込んだサービスを展開
自宅で生活する上で必要になってくる日常生活関連のお困り事をお助けするサービスです。
草取りや家の大掃除、買い物の代行、庭の手入れ、除雪やタイヤ交換、電球の交換など幅広く対応が可能です。
自宅生活を送る中で、一人ではできない、家族に頼れないといった時には頼って頂きたく思います。
【ハートサービス】
この度、令和4年3月より介護タクシー及び御用聞きサービス部門を新たに開設を致しました。
今までの部門では手が届かなかったところまでサポートの範囲を拡げ、今の生活を維持できるようにしていくためのサービスです。
専門職もいる事業所なので自宅生活での不安や、悩みもワンストップで解決でき、安心してご利用いただけます。
今後ともよろしくお願い致します。
【ハートサービス】
この度、令和4年3月より介護タクシー及び御用聞きサービス部門を新たに開設を致しました。
今までの部門では手が届かなかったところまでサポートの範囲を拡げ、今の生活を維持できるようにしていくためのサービスです。
専門職もいる事業所なので自宅生活での不安や、悩みもワンストップで解決でき、安心してご利用いただけます。
今後ともよろしくお願い致します。
これまで、ご利用者様から介護職員処遇改善加算を算定させていただいておりますが、令和2年 7月 1 日より従来の処遇改善加算に加えまして、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 加算率 1.2% を算定させていただきますことをお知らせ致します。
介護職員等特定処遇改善加算とは
介護などの障害福祉サービスを利用する人の割合が増える一方、現場を支える職員 が不足しているという現状を受けて、新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が導入されました。これは、介護の現場で働くスタッフ(主に介護福祉士)が、より快適に、そして長く働けるようにと厚生労働省が定めた制度です。
これまでも処遇改善加算等の取り組みが行われていましたが、さらに定着率の向上 を目指すことで、適正なサービスを保つという意味があり、これは単純に職員の給与改善という意味にとどまらず、適切な労働対価を支払い、適切なサービスの質を保つためにも最低限必要な費用となります。ご理解の程宜しくお願い致します。
これまで、ご利用者様から介護職員処遇改善加算を算定させていただいておりますが、令和2年 7月 1 日より従来の処遇改善加算に加えまして、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 加算率 1.2% を算定させていただきますことをお知らせ致します。
介護職員等特定処遇改善加算とは
介護などの障害福祉サービスを利用する人の割合が増える一方、現場を支える職員 が不足しているという現状を受けて、新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が導入されました。これは、介護の現場で働くスタッフ(主に介護福祉士)が、より快適に、そして長く働けるようにと厚生労働省が定めた制度です。
これまでも処遇改善加算等の取り組みが行われていましたが、さらに定着率の向上 を目指すことで、適正なサービスを保つという意味があり、これは単純に職員の給与改善という意味にとどまらず、適切な労働対価を支払い、適切なサービスの質を保つためにも最低限必要な費用となります。ご理解の程宜しくお願い致します。